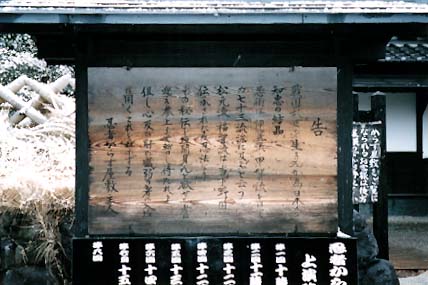|
「伊賀忍者対甲賀忍者の死闘」 [前説] (注)上演中の写真はありません。動きが早すぎて撮影できませーん。とほ〜。 |
 左/鹿島択郎さん。右/水上煌博さん。寒そう。
左/鹿島択郎さん。右/水上煌博さん。寒そう。 |
 水上さん。撮影者の好みのタイプだった様です。
水上さん。撮影者の好みのタイプだった様です。 |
 |
 |
 公演の合間は、大抵こうして遊んでいます。 |
 |
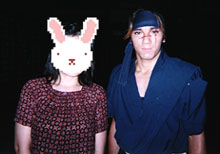 「ちゃっかり」
「ちゃっかり」
2ショット撮ってたんですよ。えぇ、まったく。 |
 |
 |
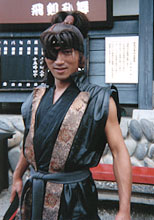 |
■ところで『虎の巻』 よく、秘伝の書物などのことを『虎の巻』と称しますが、正式な『虎の巻』とは、源 義経が鬼一法眼の娘から盗んだ中国の兵法書、『六韜三略/リクトウサンリャク』の中の一つなのだそうで。文韜・武韜・竜韜・虎韜・豹韜・犬韜の6巻からなる巻き物中『虎の巻』だけが重視され、入手した後、義経は他の巻は全て焼いてしまったそうです。 なぜ『虎』なのかというと、虎は毘沙門天のお使いだから。 毘沙門天は、古代インド神話の「クベラ」が仏教に取り入れられたもので、梵名を「バイスラバナ」。仏法の護法・護世神で、甲胄を着た武神の姿をしています。四天王、あるいは十二天の一尊として尊敬を集め、北方の守護神であり、多聞天とも呼ばれ、また、福徳財宝を司る施財神でもあり、七福神の中にも加えられている武神です。 毘沙門天が本尊の一つである鞍馬寺に行くと、渦巻き模様の「呵吽の虎」を見ることができますが、それがこの『虎』。稲荷だったら狐がいるトコロ。 |